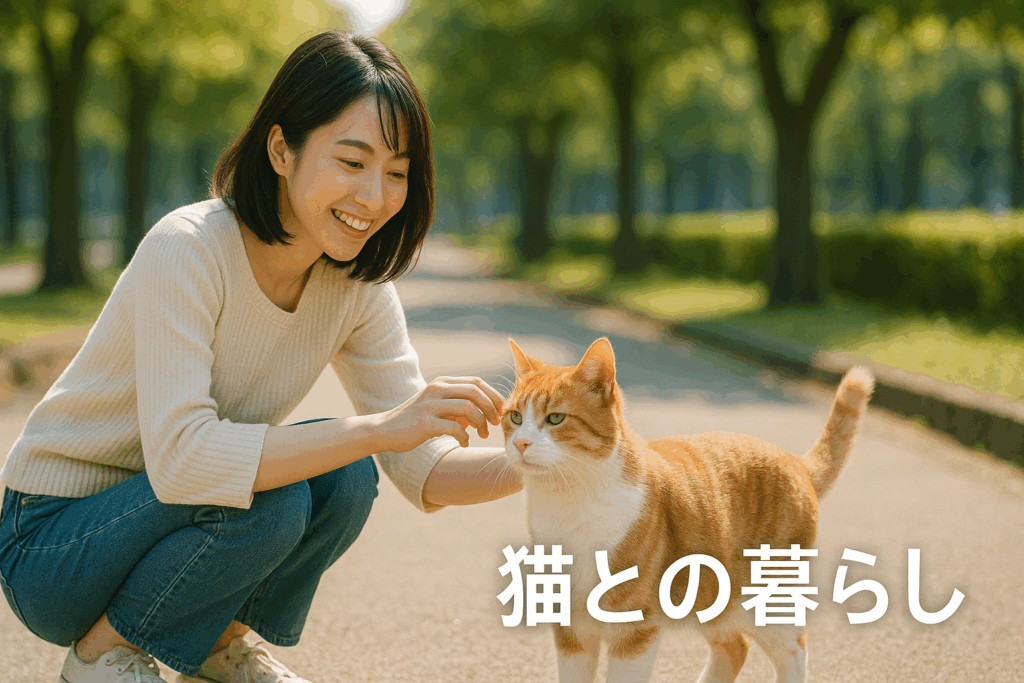
働きすぎた私の転機
終電の時間が近づくと、私はいつもスマホの時計を確認する癖がついていた。
仕事に追われ、気づけば夜の景色ばかり眺めている。
同僚は「少し休んだら?」と声をかけてくれるけれど、休む勇気すら持てないまま日々が過ぎていった。
夜の冷たい風が頬を刺すなか、マンションの前に着くと、そこにはいつもの影がある。
保護猫のミルだ。
まだ出会って三ヶ月ほどだが、帰宅のたびに玄関の前でじっと待っている。
「ごめんね。今日も遅くなったね。」
鍵を開けながら声をかけると、ミルは小さく鳴き、私の足元に体を寄せてきた。
部屋に入ると、ミルは小さな声で鳴きながら私の後を追う。
その声は叱っているようでもあり、心配しているようでもあり、不思議と胸にしみた。
疲れて帰る夜、ミルがいてくれるだけで救われるような気がしていた。
それでも仕事は待ってくれない。
翌朝も、そして翌日も、私は同じように深夜の帰宅を繰り返した。
そんな生活の中で、私はときどき、小さな命と未来のことを描いた物語サステナブル・ペットライフ 〜小さな命と、未来の約束〜の一節を思い出していた。
あの物語の主人公のように、私も目の前の小さな存在をもっと大切にできているだろうか――そんな問いが、心のどこかで静かにくすぶっていた。
ある夜、エレベーターの中で急にめまいがした。
視界が揺れ、壁に手をつく。
そのとき初めて、自分が限界を超えていることに気づいた。
それでも「ここで倒れるわけにはいかない」と、無理に足を動かして部屋に戻る。
玄関を開けると、ミルが驚いたように駆け寄ってきた。
私の顔色を見て、ただ鳴くこともなく、じっとその場に座り込んだ。
心配を隠しきれない瞳を見て、胸が締めつけられた。
ソファに座ると、ミルはそっと私の膝に飛び乗り、動かずに寄り添った。
まるで「休んで」と言っているようだった。
その静かな温もりに触れた瞬間、張り詰めていた心がゆっくりとほどけていくのを感じた。
私はミルの柔らかな背中に手を置き、深く息をついた。
「ミルがいてくれるから、頑張れたんだよ。」
そう呟いたとき、涙がひと粒、こぼれ落ちた。
休みを取るべきか迷っていたが、その週の終わり、私は思い切って上司に相談した。
驚かれると思っていたが、上司は真剣に話を聞き、「しばらく休みなさい」と言ってくれた。
気が抜けるようで、ありがたくて、思わず肩の力が抜けた。
しばらく仕事から離れ、自宅でゆっくり過ごす日々が始まった。
休みの初日、ミルはいつもより私のそばにいて、歩くたびに後ろからついてきた。
朝日が差し込む部屋で、久しぶりにコーヒーを淹れ、ゆっくりと深呼吸をする。
こんな時間があったことをすっかり忘れていた。
窓辺で丸くなるミルの姿を見て、初めて「私もこんなふうに落ち着いて生きたい」と思った。
ふと、休日に立ち寄った動物カフェを舞台にした物語ミニブタカフェの奇跡、君に会う日。のワンシーンが頭をよぎった。
あの作品の登場人物のように、私も“誰かと過ごす時間”を後回しにし続けていたのかもしれない。
ミルといる静かな午前中は、忙しさの中で失っていた「ささやかな幸せ」を、ゆっくりと取り戻していく時間になった。
昼すぎ、ミルはお気に入りの毛布の上で寝息を立てていた。
その穏やかな姿は、まるで「急がなくて大丈夫」と教えてくれているようだった。
私はノートを開き、これからの働き方を見直すために、ひとつずつ思いを書き出していった。
ミルと過ごす時間を守れる働き方をすること。
無理を前提にした生活ではなく、心と体を大切にできる選択をすること。
書きながら、ようやく本当の気持ちに気づけた。
休養が明けて職場に戻る日、ミルは玄関の前までついてきた。
私が靴を履くと、名残惜しそうに尻尾を揺らした。
「今日は早く帰ってくるね。」
そう約束してドアを閉めた。
久しぶりの仕事は緊張したが、周りの人たちは優しく迎えてくれた。
無理しなくてもいい、助けを求めてもいい、そう思えるだけで心が軽くなった。
そしてその日の夕方、私は本当に、いつもよりずっと早く帰宅した。
玄関を開けると、ミルが嬉しそうに鳴きながら駆け寄ってきた。
その瞬間、私は確信した。
この小さな存在が、私の生き方を大きく導いてくれたのだと。
ミルはただそばにいてくれただけ。
言葉は話せないけれど、心の声はずっと届いていた。
これからは、ミルを待たせない暮らしを選んでいこう。
そして何より、自分自身を大切にできる生き方を続けていこう。
ミルの優しい瞳を見つめながら、私は静かにそう決意した。
あわせて読みたい作品(関連リンク)
noteで読む後日談・続編はこちら
小説「深夜帰宅を待つ猫が教えてくれた大切なこと」の後日談は、noteにて公開しています。
休養後の主人公とミルがどんな日常を紡いでいくのか、よろしければこちらもご覧ください。



























































































































コメント