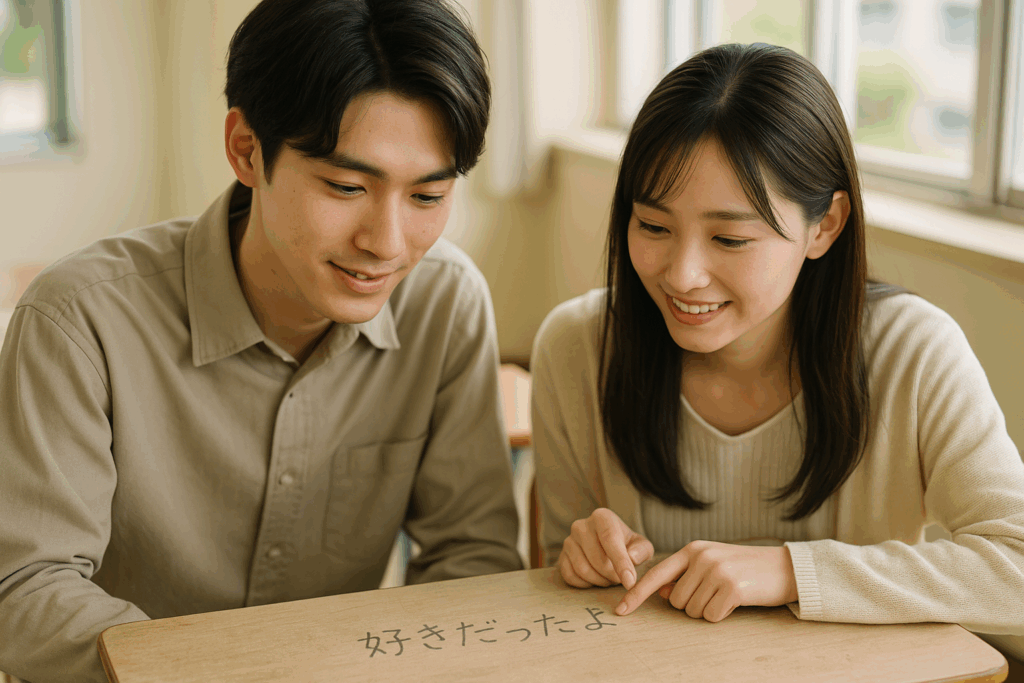
拾い直した、あの日の気持ち🌸
中学の卒業式の日、ぼくの机に鉛筆でこう書かれていた。
「好きだったよ」
名前も書かれていない、たったひとこと。
でも、その筆跡は丁寧で、どこか迷いが見えた。
誰が書いたのか、なぜ自分の机だったのか。
何度も考えたけれど、答えは出なかった。
時が経ち、社会人になった春。
地元のニュースで、母校の中学校が取り壊されることを知った。
「卒業生向けの一般公開、最終日」と書かれた小さな記事に目が留まり、ふと足が向いた。
校門をくぐると、懐かしい空気が肌に触れた。
廊下の掲示板、少しきしむ床。
あの頃と何も変わっていないのに、自分だけがずいぶん遠くに来てしまった気がした。
3年2組の教室。
ぼくの席は、最後列の窓際。
机の表面をそっと撫でると、光の角度でかすかに浮かび上がる鉛筆の痕。
「好きだったよ」
思わず息を呑んだ。
あの日の記憶が、一気によみがえる。
と、そのとき——
「……あれ? ソウタくん?」
振り返ると、そこに立っていたのはユリだった。
驚いたような顔で、少し照れくさそうに笑っていた。
「……ユリ?」
「うん。まさか会うと思わなかった」
「僕も…最後の日って知って、なんとなく来てみた」
ふたりとも、少しぎこちなく笑った。
でも、沈黙は不思議と居心地が悪くなかった。
ふと彼女が、ぼくの見ていた机に目を落とす。
そして、そっと言った。
「……あれ、私が書いたの」
時が止まったようだった。
「え……ほんとに?」
「うん。卒業式の朝、誰もいない教室でこっそり」
「名前を書く勇気はなかったけど、言わずに終わるのも嫌で」
思わず机を見つめた。
ずっと、答えのないままだった文字。
こんなふうに答えが返ってくるなんて、思ってもいなかった。
「……ずっと、誰が書いたのか気になってた」
「私も、返事がないの、ずっと気になってたよ」
ぼくはポケットからシャーペンを取り出した。
そして、彼女の文字のすぐ隣に、ゆっくり書いた。
「好きだった。あの時も。……そして今も」
ユリは目を伏せ、声を震わせながら笑った。
「そっか……やっと聞けた」
カーテンが風に揺れた。
差し込む光が、ふたりの机を静かに包み込んでいた。
──あの日伝えられなかった気持ちは、
ようやく、ここでつながった。



























































































































コメント