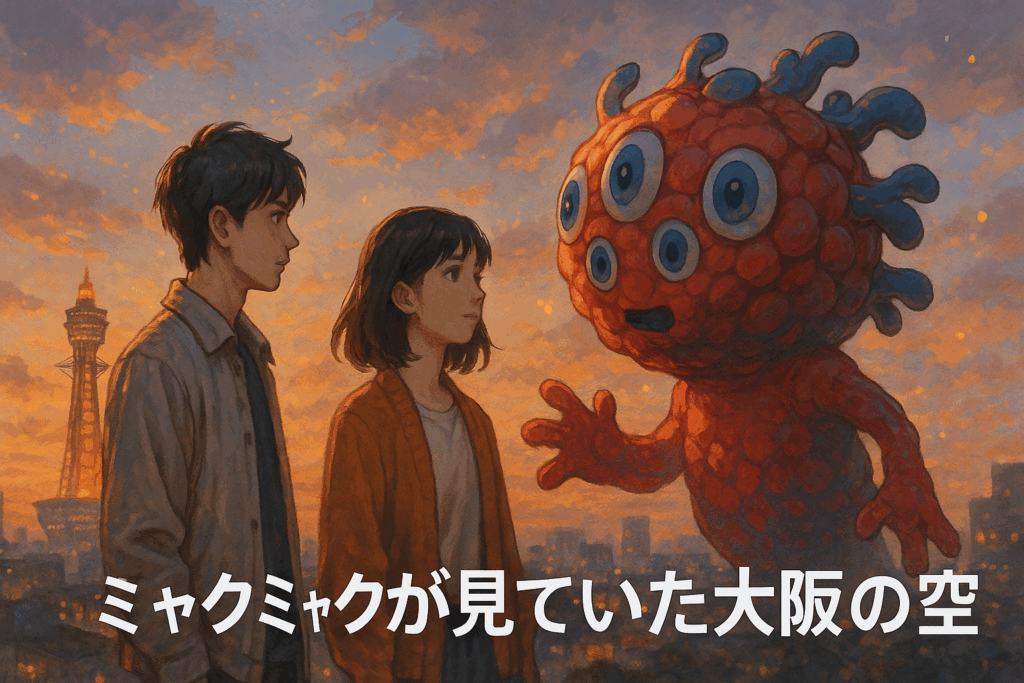
心と街をつなぐ赤い記憶
大阪の朝は、いつもどこかざわざわしている。
通天閣の下を抜ける風は、たこ焼きの香りと混ざって少し甘い。🍡
中崎町の古いアパートに住む青年・亮介は、その風を感じながら仕事へ向かう支度をしていた。
街路樹では小鳥がさえずり、ビルの谷間に生まれる微かな風がリズムを刻む。
そんな都市の呼吸は、まるで『都市コアの小鳥たちが見た夢』の一節みたいで、朝の気配をやわらかく染めていた。🐦
亮介はデザイン会社で働くグラフィックデザイナー。
最近、会社が大阪・関西万博の関連広告を手掛けることになり、彼の担当は——あの『ミャクミャク、赤い鼓動の記憶』にも通じる公式キャラクター、ミャクミャクのプロモーションだった。
「……この顔、どう見ても不思議すぎるやろ」
モニターに映る真っ赤な体、青い無数の目、にゅるっとした手。
最初に見た時の印象は“かわいい”というより、“ちょっと怖い”だった。😅
だが、亮介は仕事を進めるうちに、奇妙な違和感を覚え始める。
ミャクミャクのイラストを何度描いても、どこか微妙に表情が違うのだ。
まるで、彼の描くたびに“ミャクミャク自身が反応している”ような——そんな感覚があった。
夜。
彼は会社で一人、残業をしていた。
デスクの明かりだけが灯るオフィスで、ペンタブを握りながらつぶやく。
「ほんま、お前、どんな気持ちで生まれたんやろな……」
すると、画面の中のミャクミャクが、ふっと瞬きをした。👀
亮介は思わず椅子から転げ落ちた。
まさか、自分の目の錯覚だと思った。
けれど次の瞬間、スピーカーから小さな声がした。
「——ミャク……」
心臓が跳ねる。
冷たい汗が背中をつたう。
「……誰や? ふざけとるんか?」
「ミャク、ミャクミャク……」
声は穏やかだった。
恐怖というより、どこか寂しげで、懐かしい響きを持っていた。
亮介はゆっくりと画面に手を伸ばした。
その瞬間、画面の中から光が溢れた。💫
ミャクミャクが、液晶をすり抜けるように現れたのだ。
「えっ、ちょ、うそやろ……!?」
目の前には、実物大のミャクミャク。
真っ赤な身体が淡く光り、青い目がきらきらと動いていた。
だが、どこか優しげだった。
「ミャク……ひと、の、こころ……」
「こころ?」
「まち、の、こころ。あなた、かく……まち、の、ひと……」
亮介は呆然としたまま、頷いた。
「……俺はデザイナーや。街の空気とか、人の想いを描く仕事、やな」
ミャクミャクは静かに微笑んだように見えた。
その眼差しには、どこか祈りのような温もりが宿っていた。
それは、『万博と記憶の庭──いのちを照らす約束』に描かれる“記憶と灯り”の比喩とよく似ていた。
翌朝、亮介はその出来事を夢だと思った。
だが、机の上には赤い丸い跡が残っていた。
まるで、ミャクミャクがそこにいた証のように。🌤
日々が過ぎた。
万博の準備が進み、街には新しいビルが建ち、古い町並みが少しずつ姿を消していった。
亮介のデザイン案も採用され、彼のポスターは駅のホームを彩っていた。
そのポスターには、ミャクミャクが大阪の空を見上げて立っている姿が描かれている。
背景には古い長屋と、新しい高層ビル。
その対比が、まるで“街の記憶”そのもののようだった。
ある日、通天閣の近くで小学生の女の子がそのポスターを見ていた。
「おかあさん、ミャクミャクってな、ほんまにおるん?」
「さあなあ。でも、みんなの心の中におるんちゃう?」
そう答える母親の声が、どこかあたたかかった。
亮介はその会話を偶然耳にして、胸が熱くなった。🌇
——その夜。
彼が自宅に戻ると、部屋の窓際にミャクミャクが座っていた。
大阪の夜景を眺めながら、ぽつりとつぶやく。
「まち、かわる。ひと、かわる。でも、こころ、の、いと、つながる」
「……そうやな。変わることが悪いわけやない」
「あなた、かいた。わたし、いきる」
ミャクミャクの青い瞳が、街の光を映していた。
その瞳の中には、笑う人、働く人、泣く人、そして誰かを想う人——。
大阪という街を生きる“人の記憶”が映っていた。
亮介は小さく息を吐いた。
「ありがとう、ミャクミャク。お前が教えてくれたわ」
「なにを?」
「街も人も、血みたいに流れてる。ミャクミャク——“脈々”と、な」
ミャクミャクはにこりと笑った。😊
そして、そっと亮介の肩に触れた。
温かかった。
人の手の温もりと、街の灯りのような優しいぬくもりが重なった。
翌朝、亮介が目を覚ますと、ミャクミャクの姿はもうなかった。
ただ、机の上に小さな赤い球体が置かれていた。
それは、心臓の鼓動のように、かすかに“トクン”と光っていた。
亮介はそれを手のひらに包み、微笑んだ。
「ミャクミャク……お前はやっぱり、街の心そのものやな」
彼はその球体をペンダントにして首にかけ、出勤した。
通勤電車の窓の外、太陽に照らされた大阪の街が、今日も生きていた。
人の声、車の音、笑い声。
すべてがひとつのリズムを刻んでいた。
——それはまるで、ミャクミャクの鼓動のようだった。💓
亮介は心の中でそっとつぶやいた。
「おはよう、大阪。おはよう、ミャクミャク」
街は今日も、脈々と息づいている。
もし、誰かの落とし物みたいに置き去りにされた心があるなら、
駅前のベンチに残された白いスニーカーの物語——『忘れられた靴』——を思い出せばいい。
必ず、迎えに来る足音があると信じられるから。👟
そして、万博の会場に灯る新しい光は、過去と未来を結ぶ道しるべになる。
それは、ここで語られた約束と同じように、どこかで迷った誰かの手をそっと導く。
そんな夜には、胸のどこかで小さく響く鼓動が、また新しい出会いを呼ぶのだろう。
思い出の糸は切れない。
たとえほどけても、結び直せる。
記憶をなくしても心が覚えている——それは『落ちたヘアピン』が教えてくれた、ささやかな真実につながる。🎗️



























































































































コメント