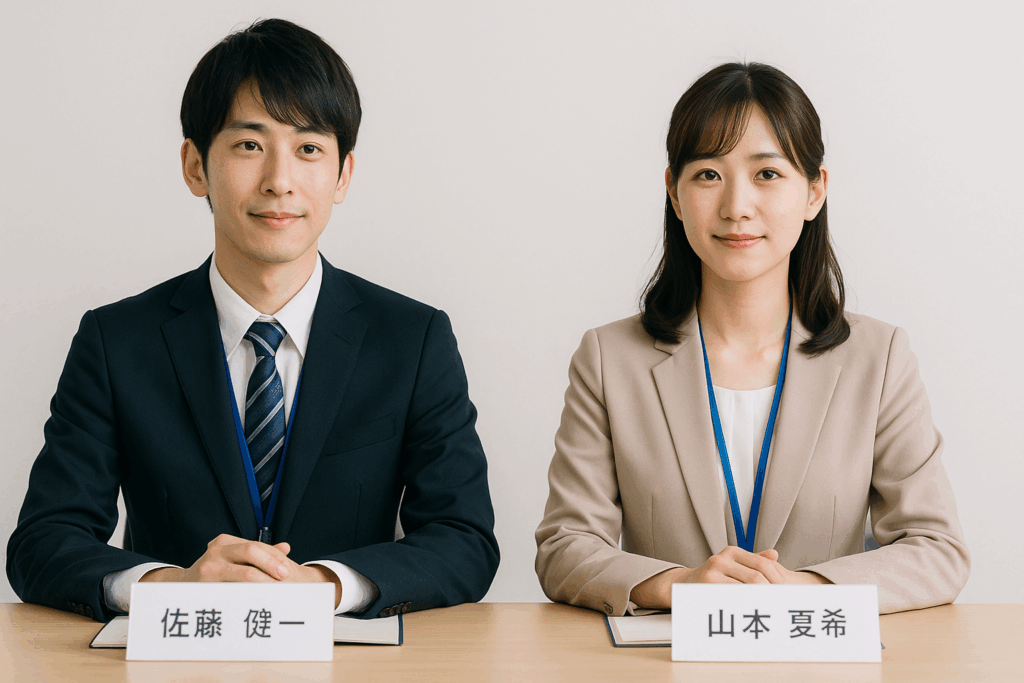
名前じゃなく、気持ちを残したかった💧
入社式の日、僕の隣に座ったのは、どこか見覚えのある女性だった。
薄茶のセミロング、静かな笑顔──それは高校のとき、たった一度だけ僕が想いを伝えた、あの夏希だった。
返事はなかったけれど、その沈黙がすべての答えだと思っていた。
「ここで会うなんて、びっくり」
そう言って笑う彼女は、僕の顔に“どこか見覚えがある”ような表情を浮かべながら、それ以上は何も言わなかった。
気づいていないふりなのか、それとも本当に覚えていないのか──それは、わからなかった。
📛
研修が始まり、隣同士の席になった僕たち。
仕事を通して、少しずつ距離が縮まり、ランチを一緒にするようになり、冗談を言い合えるようになった。
でも、彼女は高校時代の僕に触れてこない。
あの校舎の裏で「好きです」と言った僕のことを、思い出してくれているのかは分からなかった。
📩
研修机の上には、仮の名札が置かれていた。
休憩時間、夏希が席を外した隙に、僕はそっと彼女の名札の裏に小さなふせんを貼った。
『高校のとき、一度だけ君に想いを伝えました。
あの気持ちは、今も心のどこかに残っています』
休憩から戻ってきた夏希が、自分の名札を手に取った瞬間、
名札の端から、ふせんが少しだけはみ出しているのに気が付いた。
ほんのわずか、彼女の指が止まる。
その一瞬に、僕の心臓も止まりそうだった。
🕊
夕方、彼女が静かに僕に話しかけてきた。
「ねえ、昔、文芸部だった?」
思わず顔を上げた僕は、何も言えずにうなずいた。
「……あのときは、ごめんね」
彼女は少しだけ目を伏せながら、声を震わせた。
「転校が決まってて……誰かと深く関わるのが、怖かったの。
でも、あの日もらった言葉、ずっと覚えてた」
そして彼女は、僕の名札をそっと裏返して、ふせんを一枚貼った。
そのまま、何も言わずに笑って前を向いた。
名札を見た僕は、息をのんだ。
『また会えるなんて思ってなかった。
でも、もしどこかで再会できたら──そのときは、ちゃんと伝えたいと思ってたの。
忘れようとしたこともあったけど、気づけばいつも、あなたの言葉を思い出していました。
今なら、ちゃんと伝えられます──好きです』💌
あの時は言えなかった想いが、今こうして言葉になって戻ってきた。
僕は名札を握りしめ、涙がこぼれないように空を見上げた。
名札の裏。
それは、想いを言葉にするのが苦手な僕らの、小さな手紙箱だった。
ただの仮名札に見えたそれは、今、僕たちの想いをつないでくれた証になった。
🌸桜はまだ咲いていなかったけれど、僕の心には満開の花が咲いていた。



























































































































コメント