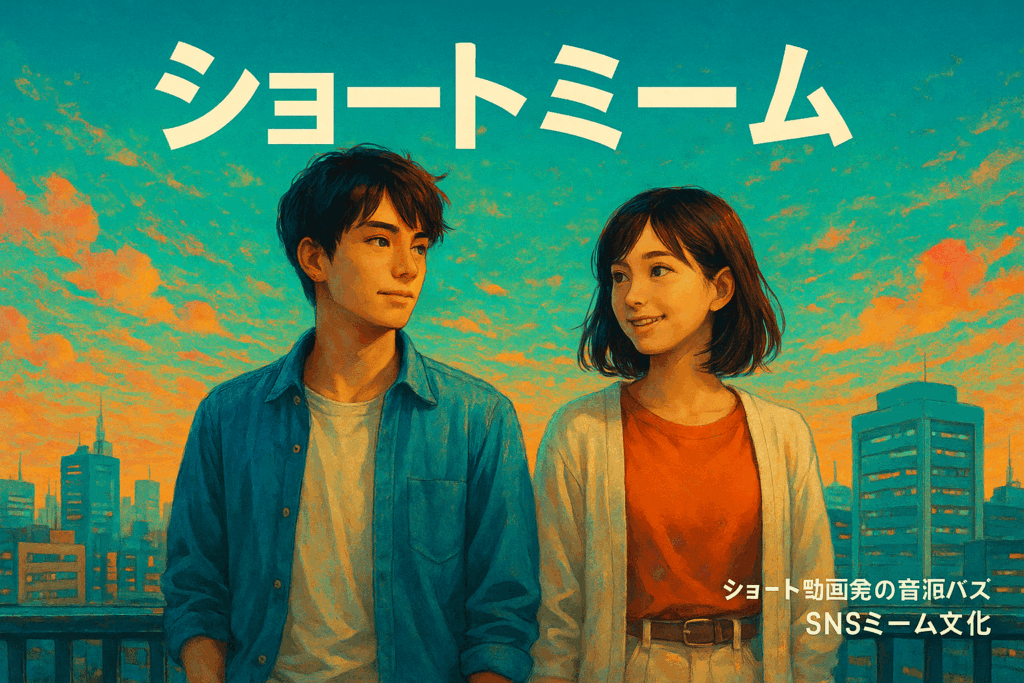
バズが繋ぐ放課後の約束
放課後の教室は、蛍光灯の白い光とスマホの小さな画面でまだ昼の続きみたいに明るかった。📱✨
窓の外で野球部の掛け声が響くたび、机の上の消しゴムが小さく跳ねる。
イヤホンから漏れたあのフックの強いビートが、机と机の隙間を流れていった。
「なぁ、見た?あの“ネコジャンプ”のやつ」
健太が椅子を半分ひっくり返した姿勢で、僕のスマホを覗き込む。
美咲は視線だけ笑って、指先でリズムを刻んだ。
「見た見た、もう百万人が跳んでる世界線」
ビートは軽いのに、胸の奥を蹴り上げるみたいに強かった。
あの三秒と少しの音が、僕らの午後を丸ごと塗り替えていく。🎶
第一章 ネコジャンプの衝撃
動画の中の誰かが、まるで床に磁石があるみたいにふわっと浮く。
タイミングは二拍目裏、落ちる足音でスネアが弾け、猫の鳴き声を加工したワンショットが空気を切る。😺
「ここ、ここで跳ぶんだよ」と健太が言い、美咲が「落ちてから笑うのがコツ」と続ける。
僕――陸斗は、何度も再生しながら、音の輪郭を目で追った。
小さな振動が胸骨に伝わって、内側のどこかを軽く撫でていく。
三秒の癖に、やけに覚えやすい。
「撮ろうよ、屋上で」
美咲の提案はいつも風通しがいい。
僕らは掃除の当番を早回しで片づけ、夕焼け色の鉄扉を押し開けた。🌆
風はまだ夏の余熱を含んでいて、校舎の壁を撫でながら逃げていく。
僕は肘でスマホを支え、美咲と健太が並ぶのをフレームの右端に寄せた。
「三、二、一」
跳ぶ。
着地の砂利がじゃり、と鳴って、スネアが少し遅れた。
動画は悪くないのに、どこかで音と体が喧嘩している。
「もう一回」と美咲。
四回目で、ようやく足とビートが握手した。
美咲の髪が弧を描き、健太の笑い声が風に溶ける。
過剰でも不足でもない、ちょうどよさが画面の向こうで光る。✨
「上げよ」
投稿ボタンに指を滑らせると、僕らの三秒は世界の川へ放り込まれた。
数字はすぐには動かない。
それでも、どこかで誰かの午後が、僕らの三秒で少しだけ跳ねるかもしれない。
そう思うだけで胸が温かくなった。💫
第二章 音の出どころ
翌朝、教室に入ると、陸上部のルカが「見たぞ」と言った。
「お前らのネコ、まあまあ跳んでたじゃん」
数値は千を超え、コメントが十を越えた。
「裏で鳴ってるベース気持ちいい」「着地の砂利音が生々しい」「どこで録ったの」
僕らは視線で合図し、廊下の突き当たりでこっそり拳を合わせた。🙌
「でもさ」と美咲が言う。
「この音源、誰が作ったんだろ」
クレジットには“NekoLoop”の文字だけ。
プロフィールには猫のアイコンと、短い「好きに使って」という一文。
無機質な軽さが、逆に気になった。🐾
「探す?」
僕らは放課後、図書室の隅でイヤホンを分け合いながら古い投稿を遡った。
鍵は古いノイズの手触りだった。
一番最初の投稿だけ、部屋の空気の匂いがする。
窓の隙間風みたいな低音の揺れと、マイクに触れた手の摩擦音。🎧
「これ、部屋録りだね」と美咲。
「たぶん、家」
健太が地図アプリを開いて、「猫の鳴き声、近所の保護施設のアカに似てる気がする」と言った。
根拠はない。
けれど、何かに触れる直前の微かな静電気が、指先でちらついた。
第三章 ホームの風と、すれ違う影
休日、僕らは駅の高架下に集まった。
線路を渡る風が、耳の内側を撫でる。
ここならベースの低いうねりが録れるはずだった。🚇
「新しいミックスを作ろう」
美咲はリュックから古いフィールドレコーダーを取り出した。
金属の表面に小さな傷がいくつもついていて、使い込まれているのがわかる。
「オリジナルの尊重と、うちらの実感の合流点」
僕はその言葉が少し好きだった。
短いのに、ちゃんと重たい。
ホームの端で、電車が通り過ぎる瞬間を待つ。
ガードのビスが震え、靴底が低い振動を拾う。
レコーダーのメーターが緑から黄色に少しだけ触れた。
そのとき、背後でルカが笑った。
「著作権警察かよ、お前ら」
ルカはスマホを掲げ、ライブ配信の画面を揺らした。
「『ネコジャンプごっこ、正義ぶってる編』。お前ら、いいやつぶるの上手いな」
血の気が引くのがわかった。
画面の向こう側で、誰かの指が連打している。
その速度が、胸の鼓動を追い越していく。💢
「やめて」と美咲が言った。
声は落ち着いていたが、指先が少し白かった。
「うちらは、ちゃんと敬意を払いたいだけ」
「敬意ね」
ルカは肩をすくめ、電車の風に髪を遊ばせた。
「数字は正義。バズったもん勝ち。音源の出どころ?誰も気にしない」
僕は言い返す言葉を探したけれど、見つからなかった。
代わりに、ホームの柱に手を当て、振動の長さを数えた。
四つ分の心拍で消える。
僕の中の何かも、ちょうど四つでしぼんだ。😶🌫️
第四章 静かに上がる
翌週、僕らの動画は数万再生に届いた。
誰かが僕らの足音をサンプリングして、更に軽いビートを重ねていた。
派生の派生は、もう原型から遠く離れていく。
しかし、ひとつだけ、耳を掴む派生があった。
ネコジャンプの直前に、わずかなブレスが入っている。
まるで、跳ぶ前に目を閉じて息を整える、あの時間。
「これ、NekoLoopの本人じゃない?」と美咲。
コメント欄は穏やかだった。
「静かに上がる感じが好き」「目立たないけど心地いい」「騒ぎじゃなくて合図」
静かに上がる。
クワイエット・アゲという言葉を、僕はそのとき初めて身体で理解した気がした。🌤️
「文化祭でやろうよ」
美咲は黒板にチョークで大きく「静かに上がる」と書いた。
「展示じゃなく、ライブ。この街の音で、ネコジャンプをもう一度生やす」
僕らは分担を決めた。
健太は映像、僕は音、そして美咲は全体の構成。
許可を取り、ベランダにマイクスタンドを立て、校庭の砂、図書室のページをめくる音、理科室の水の滴り、購買のレジが閉まる音を録った。🎤
夜、編集画面の波形が山脈みたいに並ぶ。
僕はその稜線に指を沿わせ、三秒の峠を丁寧に彫り直していった。
第五章 見えない作者
文化祭前日、学校のポストに白い封筒が入っていた。
差出人はなかった。
開けると、短い手紙と、USBメモリがひとつ。✉️
『ネコの跳ぶ前。あれ、私の部屋の隙間風でした。好きに使ってください。NekoLoop』
僕らは顔を見合わせた。
「本人?」
「でも、どうして学校のポストに」
USBを差し込むと、そこには「before_jump.wav」だけが入っていた。
波形は薄くて細い。
けれど美しかった。
音の前にある音、沈黙の手前の沈黙のような、空気の表面張力。🌫️
「ありがとうを、どうやって返そう」
僕らは考えた。
タグ付けでも、固定コメントでも、足りない気がした。
「透明なクレジットを作ろう」と美咲が言った。
「音が鳴る前に、灯りをひとつ増やす。それが合図で、敬意」
第六章 灯りの前で跳ぶ
体育館の照明がゆっくり落ちる。
スクリーンには、校内で集めた音の風景が流れ始めた。
ページの擦れる音、床を磨く雑巾の水、階段の踊り場で友達が笑う呼気。
そのすべてが、三秒の前の三秒に注がれていく。🎬
僕らはステージに立った。
僕はラップトップの前で指を浮かせ、美咲はハンドマイクを持ち、健太はカメラを肩にかけた。
まず、灯りをひとつ増やす。
スポットが観客席の右上をそっと照らし、そこに白い文字が浮かぶ。
『NekoLoop』
歓声は起きなかった。
かわりに、ざわめきがゆっくりと温度を上げた。
僕は再生ボタンを押す指に重心を集める。
before_jumpが鳴る。
たったの一秒と少し。
空気が吸い込まれ、誰もが無意識に息を整える。
そして、跳ぶ。✨
スネアが合図し、猫のワンショットが弾け、体育館の床が一瞬だけ軽くなる。
観客席の端で、小さな子が思わず立ち上がった。
その瞬間、画面の向こうとこちらが握手した。
二回、三回。
跳ぶたびに、僕の中で固まっていた何かがほどける。
数字じゃない、速度じゃない、名前のない実感が、胸骨の裏で静かに上がっていく。🌈
曲の終わりに、僕らは深く礼をした。
観客席のどこかで手を振る影があった。
猫のアイコンがプリントされたキャップ。
一瞬の光に紛れて、その人はすぐ見えなくなった。
第七章 ミームの川の先
翌朝、僕らのライブは切り抜かれ、いくつもの派生と一緒に流れていった。
「灯りを増やす」合図が真似され、いくつものbeforeが生まれた。
それでも、炎の高さを競う声は、相変わらず大きい。
ルカはというと、配信で「昨日のは良かった」と短く言った。
「数字は正義」と笑っていた彼の声が、少しだけ柔らかかった。
バズは波だ。
来ては引く。
引いたあとに残る砂の模様みたいなものを、僕らは拾い集めた。
それはタグにも、ランキングにも、アーカイブにも映らない。
でも確かに、靴底に残っている。🌊
放課後、僕らは屋上に上がった。
風は新しい季節の匂いがして、雲の縁がほんのり金色だった。
「次は何を録る?」と健太。
「誰かの名前じゃなくて、誰かの時間を録りたい」と美咲が言う。
「たとえば、宿題を始める直前の呼吸の長さ。メッセージを送る前に、指が止まる瞬間」
僕はうなずいた。
「跳ぶ前の一秒は、永遠の別名かもしれない」
僕らはしばらく黙って、空が焼けるのを見た。
通知の音は鳴らなかった。
それでも、胸のどこかで光が増えていくのがわかった。🔆
終章 合図は小さく、でも確かに
文化祭が終わった夜、NekoLoopからDMが届いた。
『灯り、見ました。ありがとう。beforeは好きに使ってください。時々、合図を増やしてください』
僕はスマホを胸に抱き、天井を見上げた。
返す言葉を何度も考えたが、結局「こちらこそ」の四文字しか浮かばなかった。
それでも指先は温かく、静かな余韻が胸に広がっていた。
翌朝、屋上に出ると、美咲と健太がすでに待っていた。
東の空は薄い朱に染まり、雲の縁が金色に光っている。🌅
「録ろう」
美咲がそう言ってレコーダーを掲げる。
健太はカメラを構え、僕は深く息を吸った。
跳ぶ前の一秒が、夜明けの空気と混ざり合う。
息を整える音、制服の袖が擦れる音、まだ眠そうな街のざわめき。
それら全部が、新しい“before”として刻まれていった。
「じゃあ、せーの」
僕らは目を合わせ、息を止め、跳ぶ前の光を胸に抱いた。
その瞬間、屋上の世界がふわりと軽くなった。
小さな合図は確かに存在し、未来へと繋がっていく気がした。



























































































































コメント