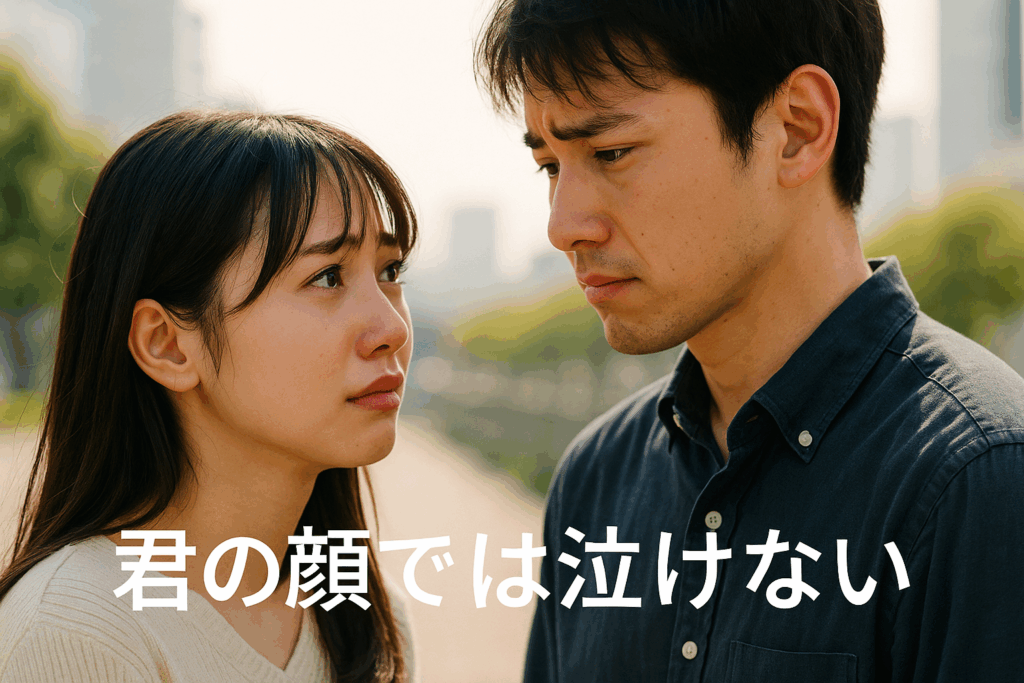
あなたの“声”で、ようやく涙がこぼれた📻💧
一年前の雨の日、俺は澪の前から姿を消した。
きちんと別れも告げずに、ただ黙って、逃げるように。
☔
理由なんて、今になってもちゃんとは言えない。
東京で内定が決まった彼女を祝福する言葉が、なぜか出てこなかった。
大学の帰り道、改札を通ろうとする澪を見送りながら、俺はたった一言だけ伝えた。
「……頑張れよ」
彼女が振り返ったその瞬間。
笑ってくれた顔を見て、ふと気づいた。
――君の顔では、泣けない。
あまりにも強くて、あまりにも優しくて、あまりにも綺麗だった。
そんな君の顔を見てたら、自分の弱さも未練も、全部飲み込まれてしまいそうだった。
🎧
俺たちは、大学のゼミで音響を専攻していた。
音で人の感情を伝える研究に、ふたりで夢中になった。
一緒にノイズを拾い、古い録音機で実験して、何時間も無言で波形を眺める日もあった。
俺は言葉が苦手だった。
だから、澪の声だけを、毎日こっそり録音していた。
笑ったときのトーン。
怒ったときの呼吸。
沈黙の中にある「好き」のような気配。
それが俺の全部だった。
でも言えなかった。
好きだなんて。
🎙
社会人になった澪は、たまにメディアに出るようになった。
声だけが流れるラジオ番組を偶然耳にしたとき、あの頃の研究の続きを、彼女が仕事にしているのを知った。
一方、俺は地方の工場で、機械のノイズ処理をするエンジニアとして働いていた。
あの日から、ずっと泣けなかった。
どれだけ想っても、どれだけ夜に耳をすませても、君の顔が浮かぶだけで、涙は止まった。
📦
春のある日。
俺のもとに、小さな封筒が届いた。
消印は彼女の実家のある町だった。
中には、USBメモリと便箋が一枚。
『見つけたよ、卒業前に録った“音”
あなたの声が入ってた
やっぱり、あなたは私にとって特別だった』
――澪。
震える手でUSBを差し込んで、再生した。
最初はノイズ。
その中に、記憶にある自分の声が混じっていた。
『……澪……、す……きだ……。』
それは、大学最後の夜、研究室で録った声。
ノイズに紛れて、ようやく届いた、あの日の「好き」。
📻
涙が、音もなく頬を伝った。
そうだ。
やっと泣けたんだ。 君の顔では泣けなかった。
でも――君の“声”で、泣くことができた。



























































































































コメント