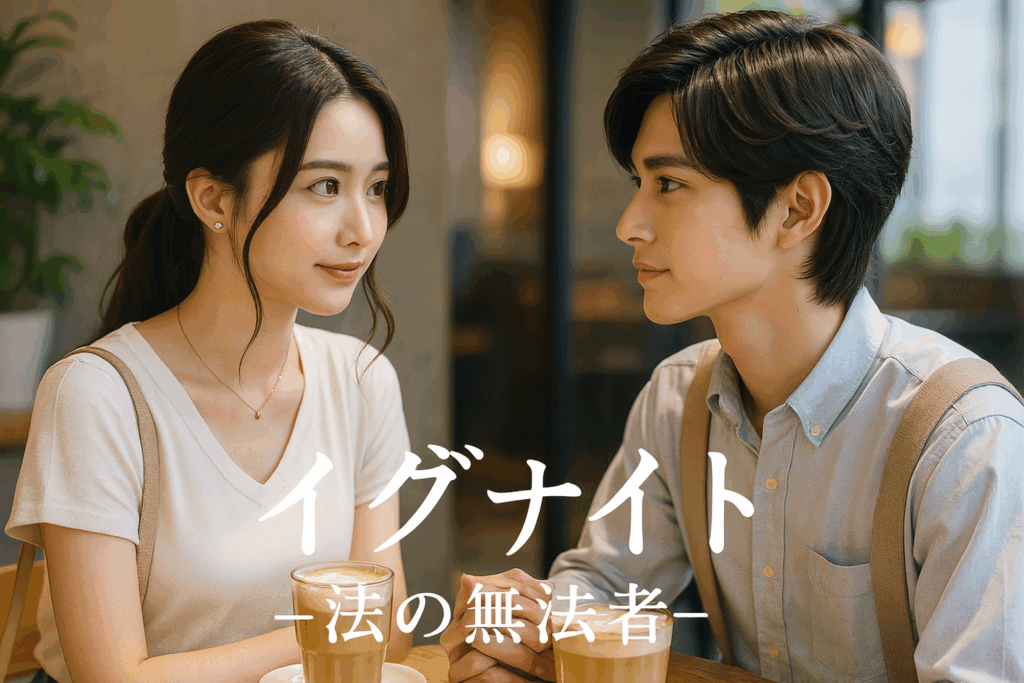
カフェラテに浮かんだ、あの日の嘘☕💔
――あのとき、好きだなんて、言わなきゃよかったのに。
千夏(ちなつ)は、胸の奥がじんと痛むのを感じながら、駅前の小さなカフェを後にした。
手にしていたレシートには、“YAMANE ATSUSHI”という懐かしい名前が印字されていた。
☕一週間前、SNSで偶然再会した篤志と「一杯だけなら」と会うことになった。
高校時代、彼は“模範生”だった。
生徒会に所属し、ボランティアに精を出し、難関大学への推薦も決まっていた。
一方の千夏は、校則違反の常連。
生徒指導室では名前を呼ばれるより先に顔で覚えられていた。
“イグナイト”――火種のように何かとトラブルを起こすその性格で、あだ名までついていた。
真逆なふたりだったのに、廊下でぶつかった小さなきっかけから、篤志はいつも彼女に声をかけてくれていた。
「おはよう」「今日も元気そうだね」
その優しさが、だんだん胸の奥を焦がすようになっていった。
だから卒業間際、思い切って言ってしまったのだ。
――「好き」って。
でも、返事はなかった。
それから音信不通になってしまい、千夏はその言葉をずっと後悔していた。
💬そして再会の日。
カフェで篤志は、懐かしそうに笑った。
「千夏、昔と変わらないね」
「あんたは変わったでしょ。真面目くんから、エリートさん?」
軽口を交わすうちに、あの頃の空気が戻ってくる気がした。
しかし、運命はまた千夏を試す。
カフェのドアが開き、スーツ姿の女性が篤志に近づいた。
「先生、そろそろ戻りませんか?」
「ごめん、今少しだけ……彼女、研修生なんだ」
そう言って、篤志は曖昧な笑顔を浮かべた。
☕千夏は気づいた。
篤志は、今の彼女に“会いに来た”わけではない。
たぶん、ただ懐かしさに浸りたかっただけ。
そして千夏も、未練に火をつけられただけ。
別れ際、彼が置いていったレシートを手に取ると、ボールペンで何か書かれていた。
――“火をつけたのは君だった。”
💥その一行に、胸がじわりと熱くなった。
だけどもう、それは過去の火種。
燃え上がることのない灰のようなもの。
「ありがとう。
じゃあ、またどこかで」
千夏はそうつぶやいて、風の中を歩き出す。
カフェのドアベルが、過去の終わりを告げるように高く鳴った。
彼女の背中はどこか晴れやかで、もう振り返ることはなかった。
イグナイト -法の無法者-。
あの頃の“罪”は、誰に裁かれることもなく、そっと胸の奥にしまわれた。



























































































































コメント