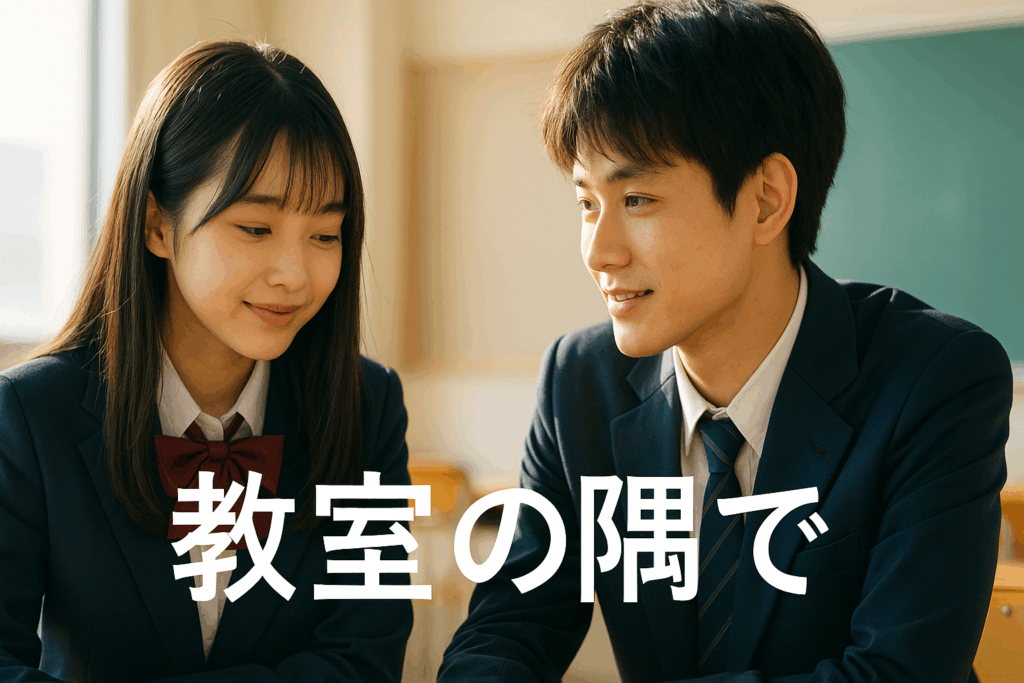
君の存在だけが、どうしても消せなかった🕊️
高校時代。
教室の隅に座っていた彼女のことを、僕は今でも忘れられない。
昼休みも放課後も、彼女はいつも窓際で静かに本を読んでいた。
誰とも話さず、黒髪を揺らしてページをめくる彼女は、まるで別の時空から来たみたいだった。
話しかけたのは、ある雨の日だった。
傘を持っていなかった僕に、彼女が何も言わず傘を差し出してくれた。
「濡れちゃうよ」
その一言で、何かが変わった。
それから、昼休みには少しずつ会話を交わすようになった。
好きな本の話、苦手な科目の話、どうでもいい校則の話。
僕にとって彼女との時間は、日常の中の奇跡だった。
でも、名前を聞くことはなかった。
お互いに、あえて聞かなかった気がする。
それでも十分だった。
彼女がそこにいて、僕だけに笑ってくれるなら、それでよかった。
卒業式の朝。
彼女は、いつもの席に座っていた。
でも、どこか寂しげだった。
「これ、渡したかったの」
手渡された小さな封筒の中には、一枚の便箋が入っていた。
「ありがとう。あなたがいてくれて、私は最後までここにいられた」
そのあと、彼女は式に現れなかった。
教室にも、廊下にも、どこにもいなかった。
僕はみんなに聞いてまわった。
でも誰も、彼女のことを知らなかった。
「え? そんな子いたっけ?」
「どこのクラス?」
担任ですら、「そんな生徒はいなかった」と答えた。
名簿にも、アルバムにも、彼女の名前はなかった。
記録にも、記憶にも、彼女の存在はなかった。
──僕以外のすべてから、彼女は消えていた。
十年後、僕は教員になり、母校に赴任した。
懐かしい教室。
ある日の放課後、生徒が忘れていった教科書を届けに戻ったとき、
ふと彼女が座っていた席を見た。
机の中に、一冊の文庫本が残されていた。
ページの間に、しおりが挟まれていた。
そこにはこう書かれていた。
「わたしも、あなたのことを忘れない」
あの日と同じ文字だった。
彼女は本当に存在していた。
記録がどうであろうと、僕の心に生きている。
教室の隅で出会った、誰にも知られない恋は、
今も静かに、僕の中で呼吸をしている。📘🌸🕊️



























































































































コメント