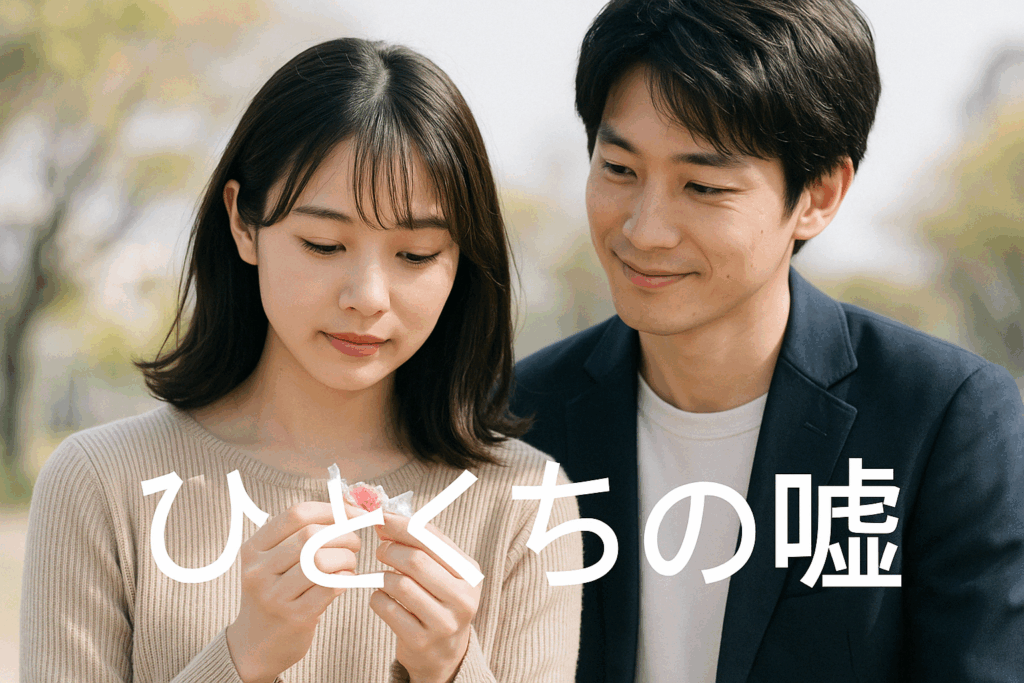
「甘くて、ほろ苦い再会の味」
「これ、好きだったよね」
彼が差し出したのは、昔ふたりでよく食べたキャンディだった🍬
春の風が吹き抜ける駅前で、私は思わず立ち止まった。
そこにいたのは、三年前に別れた彼だった。
「……元気だった?」
「まあまあかな」
私たちの間に流れる空気は、懐かしいのに、どこかぎこちない。
最後に会ったのは、大学を卒業して間もない頃。
理由は、私の“ちょっとした嘘”だった。
「覚えてる? この飴、文化祭の帰り道に……」
「雨宿りしたバス停で、最後の1個を君にあげたんだよな」
彼が懐かしそうに笑った。
私も笑ったけれど、心はちくりと痛んでいた。
あのとき、私は彼に「飴なんて興味ない」と言った。
本当は大好きだったのに。
好きって言ったら、子どもっぽく見える気がして、意地を張っただけ。
あれは、ほんの“ひとくちの嘘”。
でも、たったそれだけのことで、心が離れていった気がする。
小さなズレが積もって、大きな距離になった。
「……今さらだけど」
私はキャンディの包み紙を見つめながら言った。
「あのとき、ほんとは好きだったの」
彼は一瞬だけ驚いた顔をして、それから目を細めた。
「知ってたよ」
「えっ?」
「だって、君、嬉しそうにずっと包み紙握ってたから」
私は言葉を失った。
彼は、私の嘘を見抜いた上で、何も言わずに見守ってくれていたんだ。
駅の発車ベルが鳴る。
彼は電車に乗るため、改札に向かって歩き出した。
でも、数歩進んでから振り返った。
「また今度、正直な“ひとくち”、食べさせて」
私は、小さくうなずいた。
手の中には、少しシワになったキャンディの包み紙。
甘くて、でもほろ苦い。
それが、私たちの再会の味だった🍭✨
この小さな嘘から始まった物語が、
今度こそ、ちゃんと本当になりますように。
たった一言が言えなかった昔の私に、やっと手を振れる気がした。
そう思えたのは、もう一度彼に出会えたからだった。



























































































































コメント