
ためすぎ注意な放課後
「……んぐっ」
廊下の隅で頬をパンパンに膨らませたまま、涼太(りょうた)は立ち尽くしていた。
言いたい。
でも言えない。
なぜかって?
そこにいるのが、相沢ひなた――クラスの人気者で、しかも学級委員長。
そんな彼女に「タメ口」なんて、とてもじゃないけど無理なのだ。
*
涼太は中学からの“敬語体質”だった。
どんな相手にも「〜です」「〜ます」。
友達からは「堅すぎる」とからかわれても、それを崩すことができなかった。
でも、ひなたにだけは違った。
「タメ口でいいよ」
最初の頃、彼女は何度も言ってくれた。
でも涼太の中で、その“タメ口”は呪文のように重く、発動条件が厳しすぎた。
そんな彼に、転機が訪れる。
ある日、放課後の廊下。
ふと目を向けると、ひなたが掲示板の貼り紙をジッと見ていた。
「“溜めるな、喋れ!”……誰が貼ったのこれ」
クスクス笑いながらつぶやくその姿を見た瞬間、涼太の中で何かが弾けた。
そうだ、今だ。
タメ口、出すしかない。
言え、出せ、自分の気持ちを。
「……な、なんで、そんな貼り紙見て笑ってんの?」
……言った。
まさかの第一声が、初めてのタメ口だった。
ひなたがゆっくり振り向く。
驚いた顔をして、そして――笑った。
「今、タメ口だったよね?やっと出たじゃん」
涼太は顔を真っ赤にして頷いた。
頬のふくらみはもう限界だったのだ。
言葉を“ためる”のではなく、伝える方がずっと楽だった。
*
次の日の朝、涼太の机に一枚のメモが置いてあった。
《今日の帰り、一緒に“タメ口練習”しよ》
それは、青春の廊下で生まれた、新しい関係の始まりだった。
タメ口とは、ただの言葉遣いじゃない。
自分を出す勇気。
そして、心を近づける魔法。
それから数日、二人の放課後にはいつも「練習」という名目の会話が続いた。
「なんか、君のタメ口、面白いね」
「え、やっぱ変かな……?」
「いや、クセになる」
ぎこちない言葉は少しずつ自然に。
敬語とタメ口のあいだに揺れる距離が、少しずつ近づいていった。
これが、涼太とひなたの、等身大の“はじめの一言”だった。














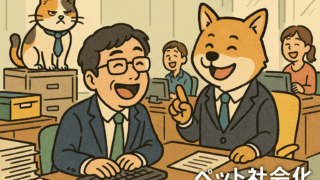




































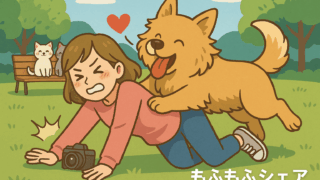





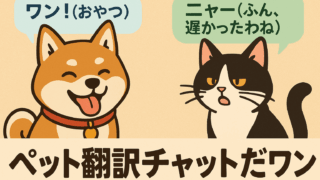











































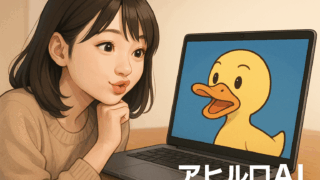





















コメント