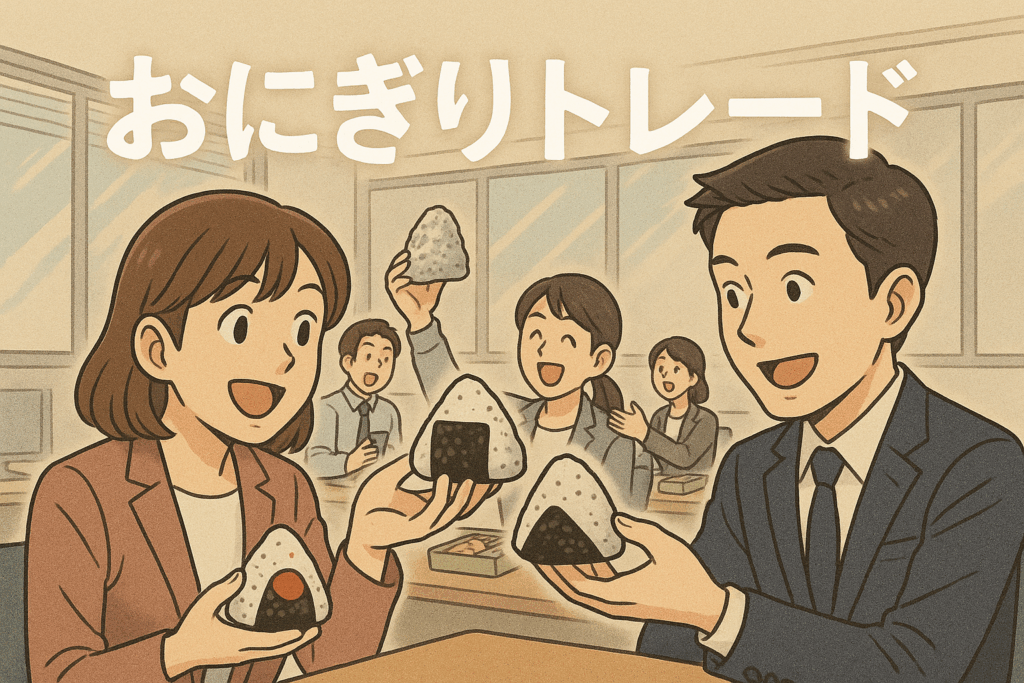
会社ランチの爆笑交換日記
昼休みのチャイムが鳴ると同時に、オフィスはちょっとした縁日のような賑わいを見せていた。
社員たちは机を寄せ合い、お弁当箱を開けたり、コンビニ袋を広げたりしている。
だが今、この会社には一つの奇妙なブームが到来していた。
「はい!今日はツナマヨ握ってきました!」
営業の佐藤が、おにぎりを包んだアルミホイルを誇らしげに掲げる。
すぐさま総務の田中が手を伸ばした。
「じゃあ私の梅干しと交換で!」
こうして始まるのが、社内で大流行している「おにぎりトレード」だ。
社員同士が持参したおにぎりを交換し合うだけのシンプルな遊び。
だが具材や握り方には持ち主の性格がにじみ出て、まるで性格診断のように盛り上がっていた。
「ん、このツナマヨ、マヨネーズ多めで濃いわね」
「佐藤くんの性格そのまんまじゃん!」
「え、どういう意味ですか!?」
笑い声が弾け、会話は止まらない。
おにぎりひとつで、こんなにオフィスが明るくなるのかと驚くほどだった。
主人公の美咲も、このブームに巻き込まれていた。
彼女が毎朝握るのは「鮭フレーク」。
安定感のある王道の具材だ。
だが交換を繰り返すうちに、意外なことに気づいた。
「美咲ちゃんのおにぎり、優しい味がする」
隣の席の先輩・村上が、そう言ってにっこり笑ったのだ。
心臓が一瞬止まりそうになる。
塩加減を控えめにしただけなのに。
そんな小さなことを見抜かれてしまうなんて。
その日から、美咲は毎朝「どんなおにぎりを握ろうか」と悩むようになった。
おにぎりを通して気持ちを伝える、そんな不思議な恋の始まりだった。
だがブームが長引くにつれ、社内にはトラブルも発生する。
「なんだよ、このおにぎり。中身が唐辛子ぎっしりじゃねぇか!」
「え!?それ私の…いや、冗談のつもりだったんですけど…」
総務の田中が、悪ふざけで作った「激辛チャレンジおにぎり」が波紋を呼んだのだ。
水をがぶ飲みしながら涙目で叫ぶ同僚。
オフィス中が爆笑の渦に包まれた。
「これ、もう完全にイベント化してるよね」
いつしか「おにぎり交換会」は毎週金曜の恒例行事になり、社員同士の距離を縮める大切な時間になっていった。
ある週の金曜日。
営業部の後輩・由衣が、やたらと大きなおにぎりを持ってきた。
「見てください!これ、ジャンボサイズです!」
机に置かれたおにぎりは、まるでソフトボール。
誰が食べるかじゃんけん大会が始まり、勝者の佐藤がひと口。
「……あれ、これ中身が…」
「え?何入れたの?」
「からあげとポテトと…あと目玉焼きです!」
「もうそれ弁当じゃん!!」
笑いが爆発し、周囲は大盛り上がり。
おにぎりの概念を超えた「進化系トレード」が新しい話題を呼んだ。
そんな中、美咲は自分の心に変化を感じていた。
最初はただの遊びだった。
でも今は、村上に「おいしい」と言ってもらえることが嬉しい。
塩加減、海苔の巻き方、具材の組み合わせ。
小さなおにぎりに、彼女は毎朝の想いを込めていた。
ある日、美咲は思い切って「ツナマヨ鮭フレーク」のハーフ&ハーフを作ってきた。
村上が一番好きな具材と、自分の定番を合わせた特別版だ。
「今日のこれ、試してみてください」
おそるおそる渡すと、村上はひと口かじり、目を丸くした。
「……うまい。これ、最強じゃないか?」
その言葉に、美咲は思わず頬を赤らめた。
そして、ある日のこと。
村上が美咲に差し出したおにぎりは、なんと「ハート型」だった。
「……先輩、これ、どういう意味ですか?」
「いやぁ、形が崩れただけ。……たぶん」
その瞬間、美咲の顔は真っ赤になった。
だが心の奥底では、もう答えを知っていた。
おにぎりの中身はツナマヨ。
一番人気で、みんなに愛される具材。
それを選んだ彼の気持ちを、美咲はしっかりと受け取った。
さらに面白いことに、おにぎりトレードの噂は社外にまで広がっていった。
「御社のランチ会、取材させてください!」と地元フリーペーパーが押しかけてきたのだ。
記者がカメラを構える前で、田中が誇らしげに語る。
「我々の会社は、おにぎりを通じてチームワークを深めているんです!」
「いや、あなたが一番ふざけてますよね!」と総ツッコミが飛び、撮影現場は大爆笑。
記事は瞬く間にSNSで拡散され、他社でも真似をする動きが出てきた。
「次は全国おにぎりトレード選手権、開催しましょうか!」
佐藤の冗談に、社員全員が「それ、アリかも!」と声を揃える。
こうして小さなランチ遊びが、会社を超えたコミュニケーションの場へと進化していく。
おにぎりトレードは、ただのブームで終わらなかった。
それは「人の気持ちをおにぎりに込めて渡す」文化として広がり、
美咲と村上の距離も、確実に近づけていったのだった。
ランチタイムの笑い声は、これからもしばらく絶えそうにない。




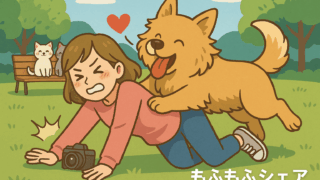






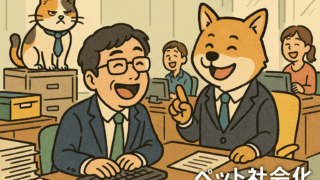















































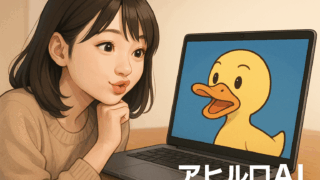




































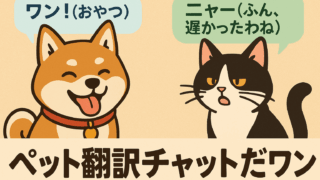

























コメント