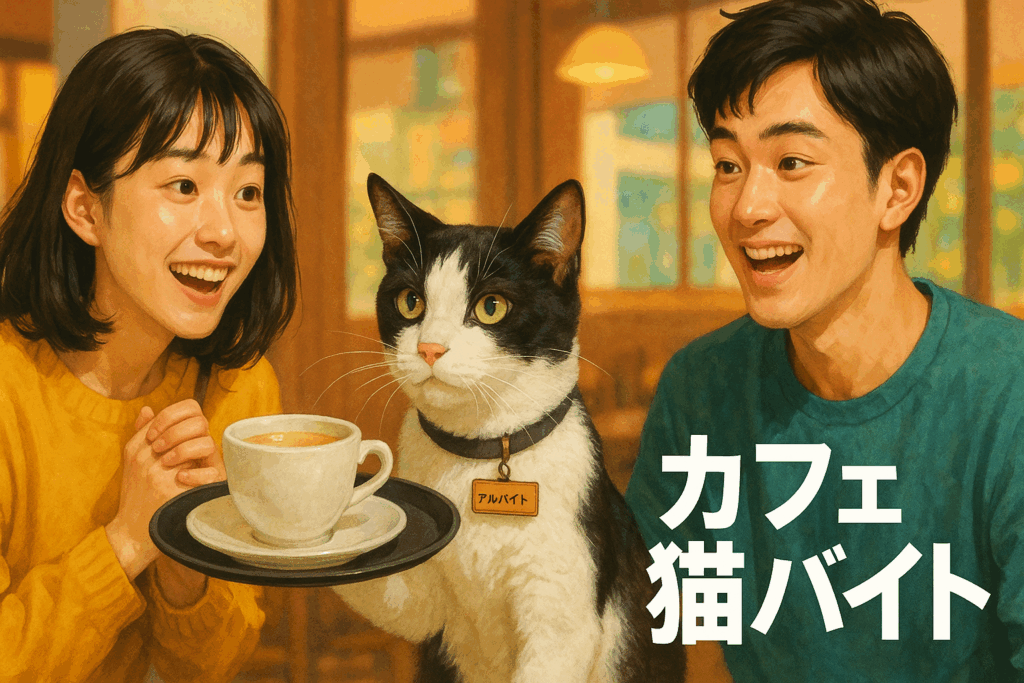
給料はカリカリだけ
カフェのドアを押すと、チリンと小さなベルが鳴った。
だが「いらっしゃいませ」と声をあげたのは、人間ではなく、白黒模様の猫だった。
「にゃー」
その猫はカウンターに座り、胸を張っている。
首には小さなネームプレートがついていて、そこには「アルバイト:ミルク」と書かれていた。
「……猫がアルバイトって本気?」
大学生の真理は思わず声を漏らした。
友人の悠人が笑って答える。
「そうそう。この店の店長が猫を正式にバイトにしたんだよ」
「時給は?」
「カリカリ二粒」
「ブラック企業すぎ!」
店内は笑い声で包まれていた。
客たちは猫ミルクの一挙手一投足を見守り、まるで舞台を見ているかのようだ。
ミルクはカウンターから飛び降り、尻尾をピーンと立てながらテーブル席に歩いていく。
その先には注文を待つカップルが座っていた。
ミルクはお盆をくわえ、よろよろと揺れながら差し出す。
「わあ、かわいい!」
「猫が店員だなんて、最高だね」
だが次の瞬間、お盆の上のミニスプーンが「カラン」と落ちた。
ミルクは一瞬きょとんとした顔をし、それからおどけるように床にごろりと転がった。

「サービス精神ありすぎだろ!」
「スプーン落としても、猫なら許せるな」
客たちは笑い、写真を撮り、すぐにSNSにアップする。
この光景こそが店の狙いであり、カフェ「ミケランジェロ珈琲店」が注目される理由だった。
まるで ネコノマド が行く爆笑カフェ珍道中 の世界をそのまま体験しているかのようだった。
しかし、すべてが順風満帆というわけではなかった。
「なあ、あの猫が客をひっかいたって苦情が来たんだが?」
バックヤードで、店長の木下がため息をついていた。
「えっ、ミルクが? そんなはずないのに」
アルバイトの沙耶が首をかしげる。
「子供がしっぽを引っ張ったらしくてな。まあ、猫の本能だから仕方ないんだが……」
真理と悠人はその会話を小耳に挟んだ。
「猫をバイトにするって、やっぱり無茶があるのかもな」
「でも、あの店の雰囲気は猫がいるからだよ」
二人は複雑な気持ちを抱えながら、ラテをすすった。
翌週、店はさらにピンチに見舞われる。
近所に新しいチェーン系カフェがオープンしたのだ。
そちらは最新のデジタル注文システムを導入し、待ち時間ゼロ。
おしゃれで便利な空間に若者が流れ、ミケランジェロ珈琲店の客は目に見えて減っていった。
「このままじゃ、うち潰れちまうぞ」
店長の木下は頭を抱えた。
「やっぱり猫をバイトにするなんて思いつきすぎたかな……」
だが、その場にいたミルクが「にゃっ!」と大声で鳴いた。
まるで「まだあきらめるな」と言っているかのようだった。
その日の夜、真理がSNSを見ていると、偶然「#猫店員チャレンジ」というタグが急上昇しているのを見つけた。

動画にはミルクが接客している姿、カリカリを「給料」として受け取る瞬間、スプーンを落としてごろりと転がる愛らしいしぐさ……。
どれも笑えて、癒されて、シェアしたくなるものばかりだった。
「これって……バズってる!」
真理は悠人にメッセージを送った。
翌日、店の前には長蛇の列ができていた。
「猫店員に会いたい!」
「ミルクにラテを運んでもらいたい!」
全国からファンが押し寄せ、ミケランジェロ珈琲店は一気に繁盛店へと生まれ変わったのだ。
それはまさに 猫カフェで大事件⁉️ 伝説の猫がやらかした のように、思わぬ展開だった。
「すごいな、ミルク。お前、SNSスターだぞ」
店長の木下が頭をなでると、ミルクは誇らしげに喉を鳴らした。
「給料、カリカリ二粒じゃ足りないんじゃない?」
沙耶が笑うと、真理がすかさず言った。
「最低でもチュール一本は必要だな」
「それもうボーナスだろ!」悠人が突っ込む。
客席では、常連客が口をそろえてこう言った。
「猫がいるからまた来たくなる」
「ミルクに会うと仕事の疲れが吹き飛ぶ」
「チェーン店にはない温かさがここにある」
その雰囲気は、まるで 猫の手も借りたい!AIが考えた小説 のワンシーンを思わせた。
気づけば、猫は単なるアルバイト以上の存在になっていた。
店の中心であり、人と人をつなぐ架け橋であり、みんなの心をやわらげる小さな救世主。
ある夜、店が閉まったあと。
木下は一人で片付けをしていた。
ミルクはカウンターの上に座り、じっと木下を見つめている。
「お前が来てから、この店も俺も変わったよ。ありがとうな」
木下がそうつぶやくと、ミルクは小さく「にゃ」と返事をした。
その声は、まるで「これからも一緒にやろう」と言っているように聞こえた。
カフェ猫バイトは今日も元気に働いている。
お盆をひっくり返して笑いを生み、客にスリスリして癒しを届け、時には真剣に「にゃー!」と注文を催促する。
給料は相変わらずカリカリ二粒。
でもその存在価値は、誰よりも大きかった。



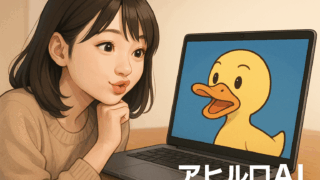







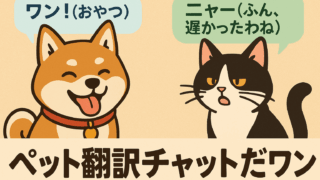























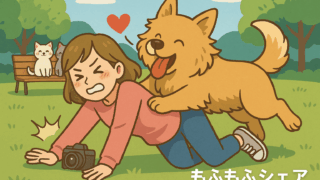























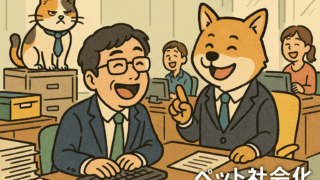































































コメント