
心まであったまる
東京都下の商店街のはずれに、古びた銭湯〈湯の華〉がある。
番台に立つ新太は三十五歳。
客は減り、光熱費は上がり、壁の富士山は色あせた。
それでも朝いちばんの湯だけは誇れる。
白い湯気が立ちのぼると、狭い脱衣所にも小さな勇気が満ちる。
その夜、裏口からずしん、ずしんと足音。
のれんをめくると、もふっと大きなカピバラが現れた。
無言で湯船をのぞき、ためらいなくトポン。
肩まで浸かると、目を細めて「ふぅ〜」。
新太は思わず笑う。
「お客さま一名、カピバラさまご来湯です。」
翌日、学生の美桜がその様子を撮影してSNSへ。
昼には店の前に列ができ、夕方には幻のラーメン屋さながらの熱気に。
いつもは静かな商店街で、行列に揉まれたおじいさんが苦笑した。
「なんだか、飲み損ねた名物みたいだねぇ。まるで」
そうつぶやいた手元で、新太は思う。
この騒ぎ、まさに幻の一杯みたいだ、と。
忙しさはうれしいが、現実はきびしい。
老朽化の指導書類が届き、改修費の多さに新太は天井を見上げる。
「終わりかもしれないな。」
湯の向こうでカピバラは相変わらず「ふぅ〜」。
その落ち着きに背を押され、彼は湯を抜かないと決めた。
三日後、美桜が駆け込む。
「クラファンやりましょう。町のみんなで!」
スマホの画面には応援の言葉が流れ続ける。
「混雑で通勤が押し寿司でも、ここでほぐれる」
そのコメントを見て、新太は思わず吹き出した。
「押し寿司って…たしかに。」
朝の電車でつぶされながらも笑って通える。
そんな人たちの物語があるとしたら――押し寿司の逆襲なんて、ぴったりかもしれない。
湯に浸かりながら読むには最高の一編だ。
改装の日取りが決まり、のれんも新調した。
オープン当日、裏口からまたあの足音。
「ゆず。」
いつのまにかそう呼ぶようになったカピバラが、迷いなくトポンと沈む。
「ふぅ〜。」
歓声と拍手。
湯気がぱっと明るくなる。
新太は胸のどこかで、通信状態の悪かった心が一気につながるのを感じた。
まるで背中に小さなアンテナが生えたみたいだ。
そんな“つながり”の空気を感じる夜は、タイトルを眺めるだけでも楽しい。
ネコの背中Wi-Fiでつながる若者――その言葉の響きだけで、湯上がりの会話がひとつ増える。
日々の番台は相変わらず忙しい。
「人手が足りないですね。」
美桜が笑うと、新太も肩をすくめる。
「猫の手でも借りたいよ。」
「じゃあ猫の“店長”でも。」
商店街では猫が話題の主役になることも多い。
たとえば失踪騒ぎの顛末が痛快な、猫カフェで大失踪!みたいに。
物語を肴に湯がぬるくなるまで語り合う夜は、ここが最高の喫茶店に思える。
ある雨の夜、泣きはらした目の女性がひとりで来た。
湯に肩まで沈め、静かに目を閉じる。
ゆずがそっと近づき、鼻でちいさく水を鳴らした。
「ふぅ〜。」
その音に合わせるように、彼女の呼吸が整っていく。
「ありがとう。」
湯上がりに残した一言で、今夜の湯は名誉を得た。
帰り際、カウンター脇の貼り紙に目がとまる。
“ペットと人が心を交わした日々の話題”も、ここでよく浮上する。
たとえば、はじめて既読の通知が届いた夜を描いた、ペット翻訳チャット犬が送った初めての既読。
これを読めば、ゆずの「ふぅ〜」が別の言葉に聞こえてくるはずだ。
そして、ときどき番台の若い常連が言う。
「気力が尽きたら、笑えるやつを読みます。」
彼が最近すすめてくれたのは、リモート時代の“もふもふ観察記”。
湯上がりの牛乳を飲みながら、その話を思い出す。
タイトルは――ハムスターリモート観察で人生逆転!?。
小さな背中が回し車をこぐ姿を想像するだけで、明日をもう一日、進める気がしてくる。
夜、戸締まりの前に新太は湯気を吸い込む。
「明日ものぼせない程度に、がんばろう。」
ゆずが返事のかわりに「ふぅ〜」。
その一音で、今日のページがやさしく閉じる。
ここは、湯でほどけた心がそっと立ち上がる場所。
白い湯気の向こう、明日も誰かの肩が軽くなる。

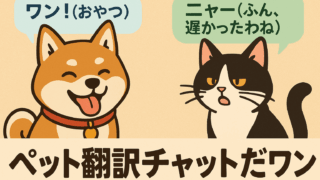




























































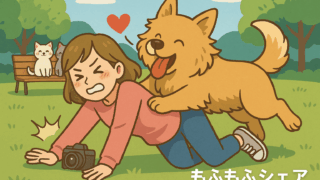




























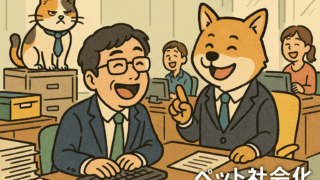























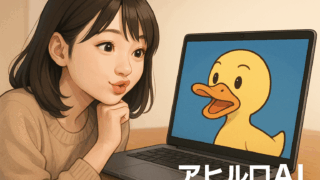







コメント